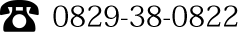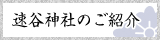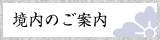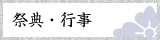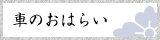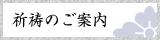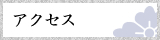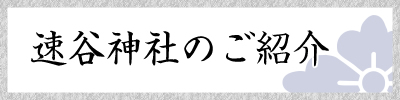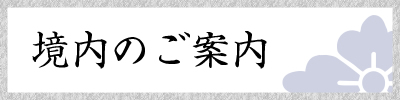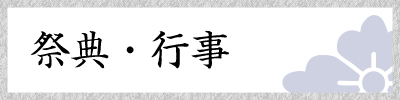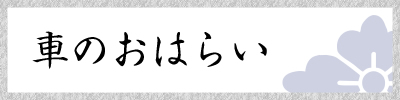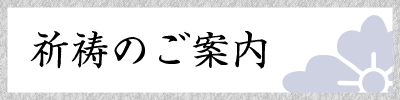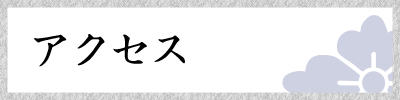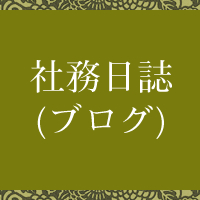創建1800年大祭に寄せて
速谷神社 宮司 櫻井建弥
速谷神社は今年10月12日、畏くも天皇陛下より「幣帛(へいはく)」と呼ばれる神への捧げ物をいただいて、「創建千八百年奉祝奉幣祭」を斎行いたしました。
この佳節にむけて令和三年から記念事業を進め、一の鳥居、儀式殿、玉垣をはじめとする諸建物の建替、修復ならびに駐車場拡張などの境内整備を行い、工事は全て無事完成しました。
これもひとえに氏子崇敬者の皆様方の篤いご崇敬、物心両面にわたる多大なるご支援の賜物と衷心より感謝と御礼を申し上げます。
さて当社の歴史を改めて振り返りますと、その歴史はたいへんに古く、平安初期の文献に、第13代の成務天皇の時代に朝廷から「安芸国造(あきのくにのみやつこ)」に任じられたとあります。国造とは古代、その地方を統治した豪族に贈られた称号です。安芸国造は安芸国を支配し、速谷の神を祖先神としてまつった大豪族でした。そこから当社は少なくとも1800年を越える歴史があり、安芸国で最も古い神社とされています。
また平安時代にまとめられた全国の神社の一覧表『延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)』によれば、当社は朝廷から直々に年4回の幣帛を受ける「官幣大社(かんぺいたいしゃ)」として登場します。こうした殊遇を受けたのは、中国、九州地方では当社だけです。
当社が最高の待遇を受けたのは、安芸国造が古代の大動脈である山陽道や瀬戸内海の制海権を握り、さらに九州や朝鮮半島に備える西の要として、出雲や吉備への抑えとして、大和政権の頼もしいパートナーであり、その祖先神に最高の礼を尽くしたとする説が有力です。
しかし、平安時代も末期になると対岸の厳島神社が平家一門の信仰を集め隆昌します。また中世に起こった承久の乱では上皇方にくみした安芸国造の子孫たちの多くがその領地を失い、さらに関ヶ原合戦の功で芸備の大守となった福島正則の領地経営のなかで社領を没収されるなど、当社は衰退の途をたどります。江戸時代に広島藩が作成した地誌『藝藩通史(げいはんつうし)』には、
福島氏、社領を没してより、殿宇頽いせし
とあり、この時代、社殿が大いに荒廃していたことがわかります。
古代からつづく大社といえども、その所在がわからなくなった神社は決して少なくありません。しかし当社には再興の転機が訪れます。福島氏改易後の正保3年(1646)、広島藩主となった浅野光晟は、かねてより神道書『神祇宝典(じんぎほうてん)』を執筆中だった徳川御三家筆頭尾張の徳川義直から延喜式名神大社の速谷神社について尋ねられ、至急家臣に調べさせます。
そして所在や由緒を確認したうえで、2年後にはさっそく藩費をもって社殿を造営し、以来、広島藩の篤い崇敬がつづくことになります。
明治にはいると、神社を「国家の宗祀」とする明治政府の政策で、「近代社格制度」が新たに整備されます。そして速谷神社には、広島県出身の佐上信一内務省神社局長ら有識者を中心に顕彰、社格の昇格、社殿造営の動きがはじまります。
大正時代の境内拡張工事には、近隣の24の町や村から4千人を超える勤労奉仕の希望があり、樹木の寄進も県内各地から2千本に達したことが記録されています。そして広島県民の強い願いが実を結び、大正13年(1924)、県内で厳島神社に次ぐ高い社格となる「国幣中社(こくへいちゅうしゃ)」への列格をはたし、現在へと続いています。
地元広島の神として長い歴史を紡いできた当神社は、先人より連綿と受け継いできた信仰と伝統を次世代に守り伝え、今後とも多くの人々から親しまれ心の拠り所となる神社を目指してまいります。
皆様方には、これからも当神社への変わらぬご崇敬の御心をお寄せいただきますようお願い申し上げます。
第26号 令和6年11月1日