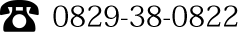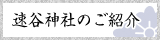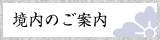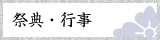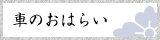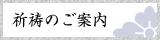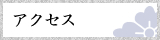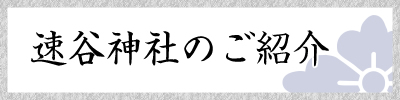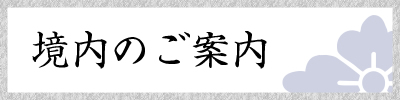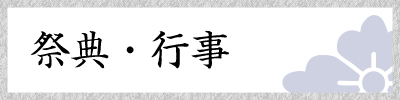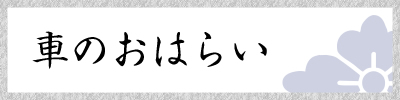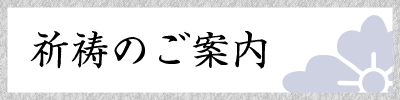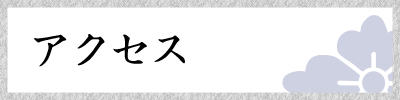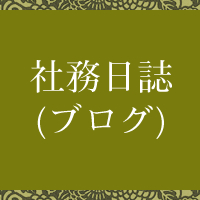戦後八十年によせて
速谷神社 出仕 網岡茉弥
《はじめに》
はじめまして。速谷神社出仕の網岡茉弥と申します。
私は三重県伊勢市にある皇學館大学文学部神道学科にて、神職を志して四年間学び、このたびご縁をいただき、令和七年四月より速谷神社に奉職しております。皆さまが心地よくお参りいただけるよう、日々努めてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
さて、本年は戦後八十年という節目の年です。この機に、靖国神社や護国神社にお祀りされている英霊について、私なりの考えを交えながらお伝えさせていただきたいと思います。まだまだ未熟ではございますが、靖国神社での奉仕を通して得た学びも含めて申し上げます。
《靖国神社について》
靖国神社は、明治二年、明治天皇の思し召しにより「招魂社」として創建されました。
明治七年、明治天皇が初めて御親拝された際にお詠みになられた御製があります。
「我国のためをつくせる人々の 名もむさし野にとむる玉かき」
このお歌からも分かるように、靖国神社は、国のために命を捧げられた方々の御霊を慰め、その事績を後世に語り継ぐために創建されました。明治十二年に「靖国神社」と改められ、明治天皇の命名による「靖国」という社号には、「国を靖(やす)んずる」、すなわち「祖国を平安に保つ」「平和な国家を築く」という願いが込められています。
靖国神社には、戊辰戦争などの国内戦から大東亜戦争に至るまで、国のために尊い命を捧げられた246万6千余柱の御霊が祀られています。そこには軍人だけでなく、従軍看護師や勤労動員中の学徒、民間人や軍属、シベリア抑留中に亡くなられた方、戦後に戦犯として処刑された方々の御霊も含まれています。
《祀られる英霊》
私が靖国神社にて奉仕させていただいた折、神職の方からいただいた言葉が強く印象に残っています。
「私たちはただ慰霊をしているのではありません。英霊を“神”としてお祀りしているのです。」
国のため、家族のために命を捧げるというのは、並大抵の覚悟では成し得ないことです。その行為に敬意と感謝を捧げるべきだという教えは、私の心に深く刻まれました。さらに、英霊ご本人のみならず、そのご家族、妻や兄弟姉妹の想いまでも大切に祀っていくことの重要性も語られました。
靖国神社は、「二度と戦争を起こさない」という不戦の誓いを胸に刻む場所であり、平和への祈りを捧げる場所でもあります。
また、参拝に訪れたご遺族の方々が、「今年もお父さんに会いに来られてよかった」と静かに語られていた姿が、今も忘れられません。
靖国神社は単なる慰霊施設ではなく、精神的なよりどころであり、歴史を語り継ぐ場でもあります。戦後、多くの論争があったとしても、「命を懸けて国を守った人々を忘れてはならない」という思いは、今も多くの人々の心に生き続けていると感じます。
《靖国神社と護国神社》
靖国神社と同様の使命を持つ神社が、全国にございます。それが各都道府県に設けられている「護国神社」です。もともとは各地の招魂社として創建され、戦後に「護国神社」と改められました。
護国神社には、地域に縁のある戦没者の御霊が祀られています。
私たちにとって身近な広島護国神社には、勤労動員中に原爆で命を落とされた動員学徒や女子挺身隊の御霊もお祀りされています。
靖国神社が全国の英霊を祀る中央の神社であるのに対し、護国神社は地域の英霊を身近に感じる場であり、どちらも「国に殉じた人々を忘れない」という精神を共有しています。
《おわりに》
戦後八十年という時を経て、戦争体験を直接語ってくださる方々が少なくなる中で、私たちは「記憶をどう継承していくか」が問われています。
靖国神社や護国神社を訪れ、その場に込められた思いや歴史に触れることは、単なる過去への追憶ではなく、「今をどう生き、未来へ何を伝えるか」を考える機会でもあります。
戦争を賛美するのでは決してありません。しかし、あの厳しい時代に「国を想い、家族を守るため」に命を捧げた人々の覚悟と行動を、私たちは静かに受け止め、感謝と鎮魂の思いを忘れずにいたいと思います。
終戦から八十年が経った今もなお、私たちの平和な日常は、英霊の歩まれた道の上に築かれているという事実を、決して風化させてはなりません。
皆さまもぜひ、機会がございましたら靖国神社や護国神社にお参りください。
そして、原爆の日である8月6日・9日、終戦記念日の8月15日には、黙祷を捧げ、戦没者の御霊に感謝し、これからの平和を祈っていただければ幸いです。
第27号 令和7年8月10日